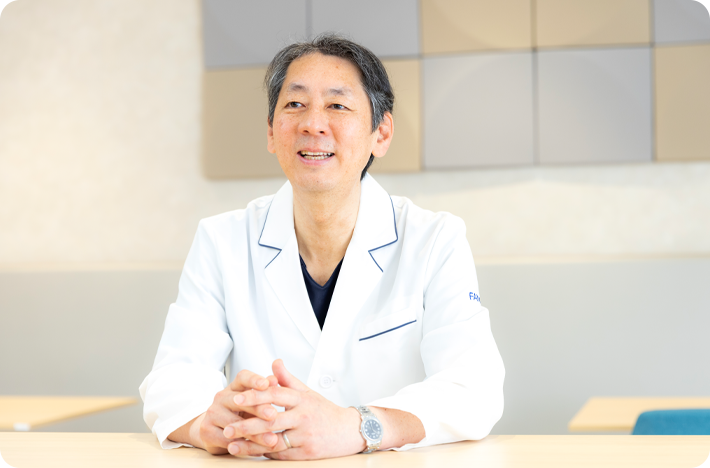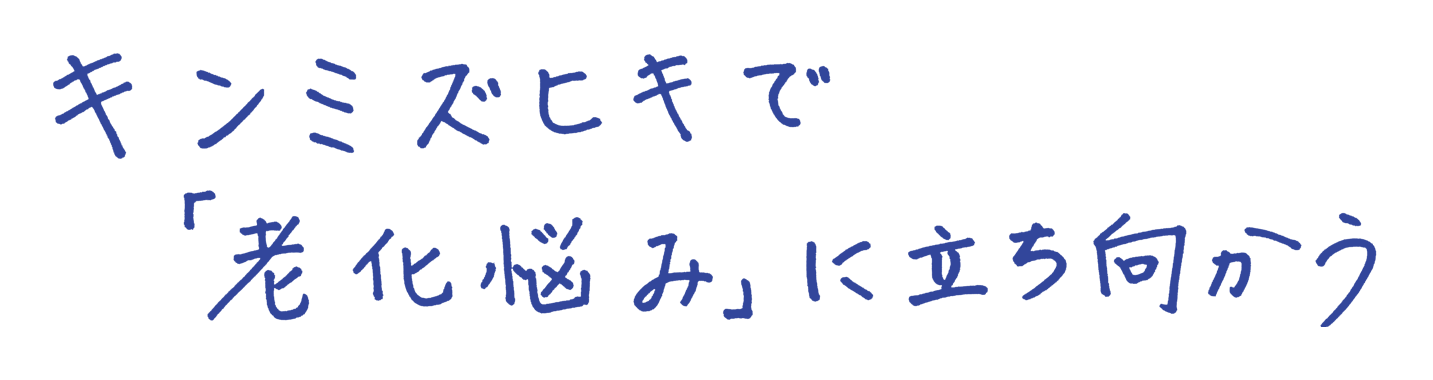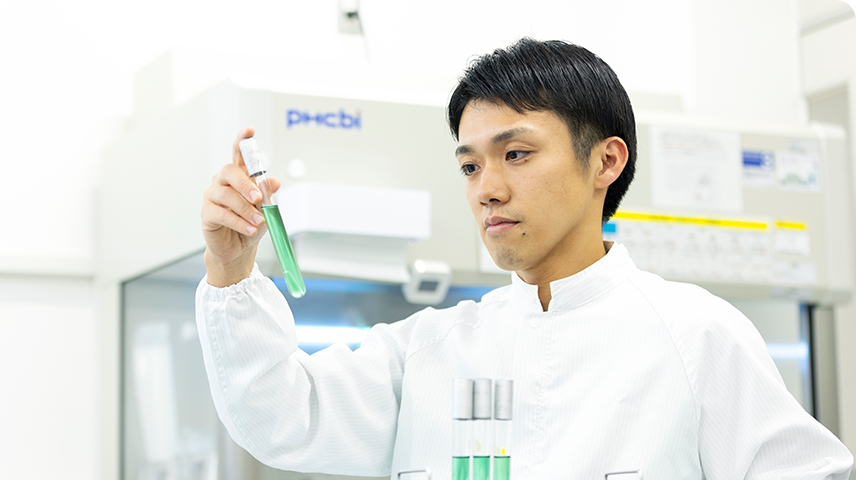CHALLENGE
未来への挑戦
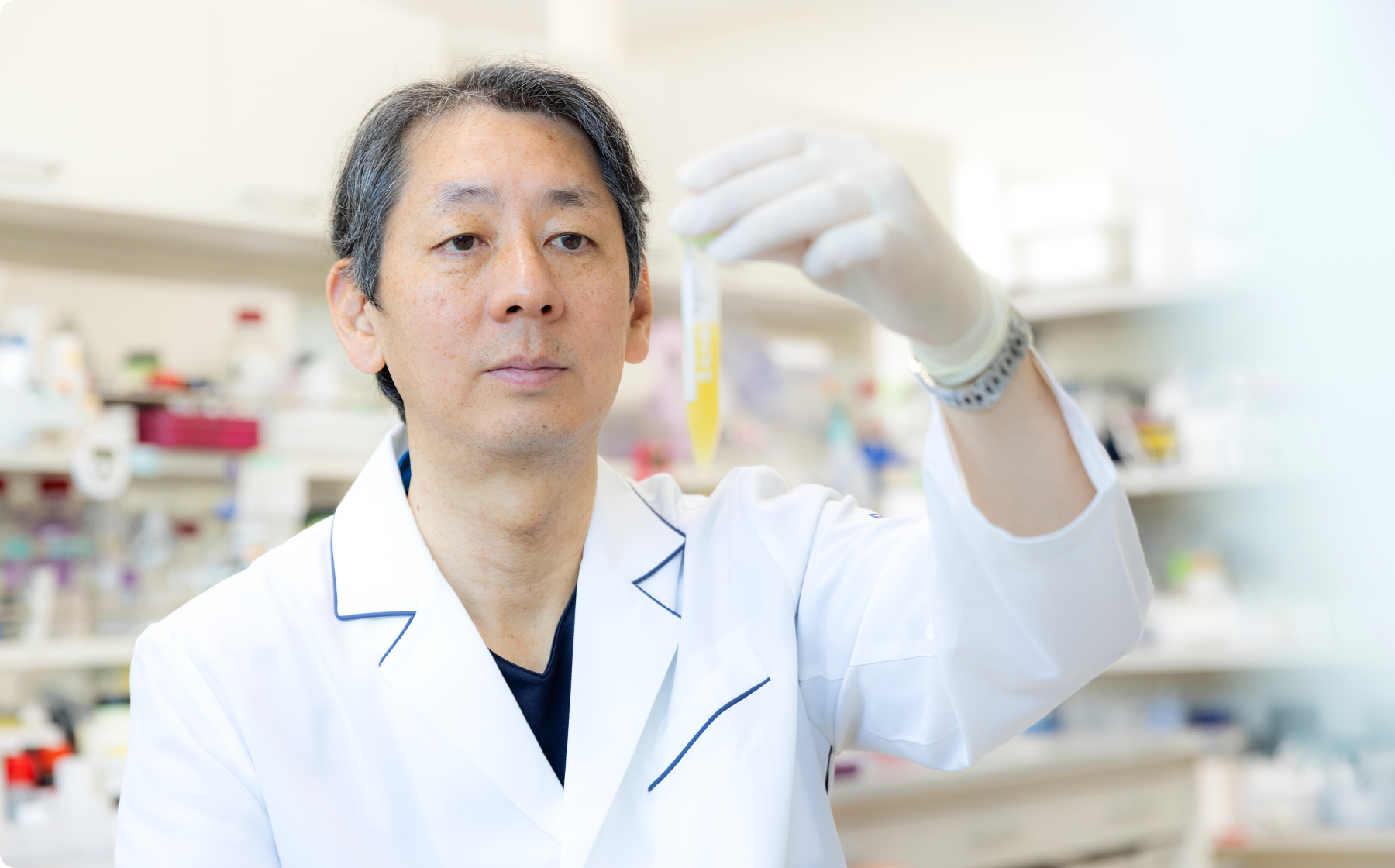
総合研究所 基盤技術研究センター
渡邉 知倫
万人に平等に訪れ、避けがたいもの―それが「老化」。健やかに、ゆっくりと年齢を重ねたい…。そんな願いを叶えるべく研究を続けてきた渡邉が巡り合ったのは、バラ科の植物「キンミズヒキ」。老化細胞に働きかけると考えられる革新的な成分の発見には、研究者の“ひらめき”が大いに役立ちました。

人類共通のテーマである「老化」に、真正面から向き合う
誰もが持つ、年齢を重ねても、健やかで明るい毎日を送りたいという想い。ファンケルでは、「年齢とともに生じる健康と美の課題への対処」に長年取り組んできました。渡邉は、研究員として健康食品に関する基礎研究から独自原料開発、そして製品化にまで携わってきました。
渡邉:私が研究職についたのは、もともと新しいものを発見することに喜びを見いだす性分だったことが大きいと感じています。瀬戸内海の島で生まれ育ったので、海や山で遊びながら、そこから珍しいものを見つけるのが遊びの中心でした。そんな幼少時代を過ごしたので、おのずと探求心が育ったのかもしれませんね。
ファンケルに入社する以前は、製薬会社で新薬の開発に携わっていたこともありましたが、新薬として世の中に上市できる可能性は非常に低く、かつ膨大な時間がかかり、そこに葛藤がありました。ある時、研修の一環で認知症の患者さんやその家族と話す機会があり、治療だけでなく日常から対策していくことの重要性を痛感しました。その時の想いを胸にファンケルに入社し、今こうして健康食品の開発に取り組んでいます。
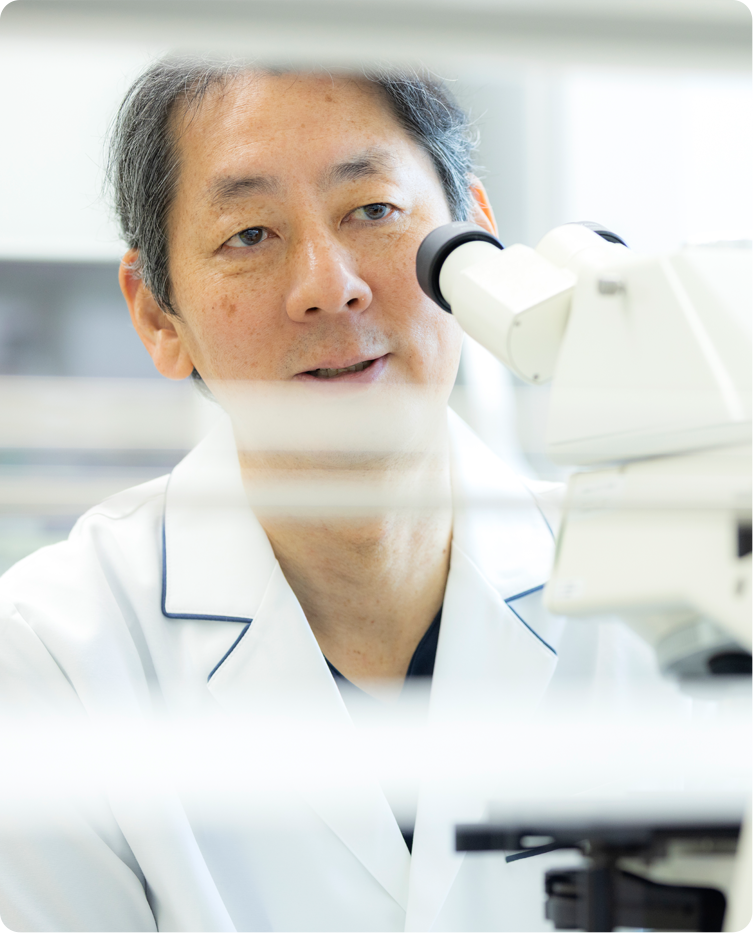
ファンケルに入社してからは、脳と老化の関係について研究してきました。生物にとって避けられないものと考えられてきた「老化」に対し、アプローチする方法がないものだろうかというのは、自分にとって長年のテーマ。老化には複数の要因が絡み合っていますが、その一つが「細胞の老化」です。老化が進んで分裂が停止した細胞(=老化細胞)が加齢とともに体内に蓄積することで、体の機能低下やさまざまな悩みを引き起こします。この老化細胞を体から取り除くことができれば、人体のさまざまな機能を改善できる可能性があるのではないだろうか。老化細胞の除去に有効な成分はないだろうかと考えたのです。
そこで、4,000種を超える食品素材ライブラリーの中から手作業で一つひとつの成分評価を行い、ついに見つけ出したのがキンミズヒキという植物でした。

食品素材ライブラリーには、冷凍された素材が保存されています
研究者としての“ひらめき”が導き出した、世界初※のエビデンスを持った機能性表示食品
古くから健康維持や料理に使われてきたバラ科の植物キンミズヒキを発見した背景には、“幸運な偶然”があったと言います。
渡邉:実を言うと、初めから老化細胞に着目していたわけではありませんでした。キンミズヒキは神経細胞を活性化する作用があることから、脳機能対策の素材を探していた時に見つけたもの。研究のプロセスで、神経細胞の活性化以外にもさまざまな作用が見られるようになり、どうも老化による機能低下に対する作用につながっているのではないかとピンときたんです。ここから老化の原因の一つである老化細胞への作用検証を行うことになりました。
この発見は、研究者としての勘が働いたとしか説明できないのですが、普段から目にしたもの成分を調べるクセも役立ったかもしれませんね。例えば、愛犬の散歩に毎日出かけるのですが、珍しい草花を見かけた時には「この植物に含まれる成分は何だろう、何かに活用できないかな?」と、愛犬を待たせて考え込んでしまうこともあります(笑)。
ヒト臨床試験においてキンミズヒキ由来アグリモール類に老化細胞除去作用があることが世界で初めて論文報告された(PubMed及び医中誌Webの掲載情報に基づく)。

日課の愛犬とのお散歩
偶然の出合いがきっかけとなり、渡邉が一人でスタートさせたキンミズヒキの研究は、その後、専門スタッフ数名による「ファンケル 加齢研究チーム」として活動の幅を広げていきました。
渡邉:脳機能素材の探索から数えると約10年の歳月を費やし、有効性データを取得しながら、独自原料の開発を並行して進めました。開発の段階では多くの壁にぶつかりましたね。
例えば、キンミズヒキに含まれる有効成分は非常に少なく、それをどう濃縮するかが課題になったり、産地による品質のばらつきが大きく、成分の種類や含有量が安定しているキンミズヒキを見つけるのに苦労したり。ピペット(液体を一定量正確に移し入れるための器具)で膨大な数のサンプルを抽出して手作業で測定を繰り返す日々が続き、けんしょう炎になってしまうのでは…、と不安になるくらいでした。
また、当時は血液中にある細胞の老化の程度を評価する方法が十分に確立されていなかったため、私たちの研究チームは測定方法をゼロから作り上げることに挑戦しました。
評価法の開発では、さまざまな血液サンプルを使いながら、何度も試行錯誤を重ねて、最適な手順や評価基準を見つけ出していきました。実はその過程で、理想的なサンプルに出会えたことが、実験をスムーズに進める大きな助けになったんです。完成した評価方法は、今ではファンケルだけが持つ独自の技術となっています。
こうして課題を一つずつクリアしながら、臨床試験においてヒトで有用性が実証できた時には、チーム全員で喜び合いました。「こんなに良い結果が出ていいのかな?」、「本当に正しいデータなの⁉」という、想像していなかったことがどんどん出てくるドキドキ感に、メンバー全員でのめり込んでいきましたね。細胞レベルの実験だけではなく、ヒトで確認できたことが一番大きな成果。これまでの長い研究課程を振り返っても、最も「やったぞ」という手ごたえを感じた瞬間だったと思います。

キンミズヒキの研究に取り組んだ「ファンケル 加齢研究チーム」の皆さん
「キンミズヒキ」のさらなる力で、毎日をイキイキと!
世界が注目する加齢研究に、新たな道を切り開いたファンケル 加齢研究チーム。キンミズヒキを中心としたプロジェクトは、まだまだ続きます。今日よりも明日が、そして未来がもっとイキイキと輝く日々であるように、研究者としての好奇心と挑戦心は尽きません。
渡邉:キンミズヒキには、老化細胞除去以外にも、長寿遺伝子の活性化やオートファジー(細胞の自己浄化機能)の促進など、将来的にはさまざまな研究の進展が期待できます。今後の研究によって明らかにしていくことで、より多くのお悩み解決につながればいいなと考えています。そして、キンミズヒキを中心に、その他の素材やサービスを合わせることで、皆さんが健康でイキイキと年齢を重ねていく手助けをしていきたいと思っています。